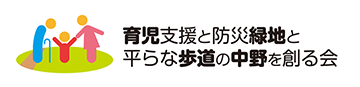カテゴリ:区議会での質疑
中野区人権及び多様性を尊重するまちづくり条例、中野区子どもの権利に関する条例
第12号議案 中野区人権及び多様性を尊重するまちづくり条例 第28号議案 中野区子どもの権利に関する条例 ○議長(内川和久) これより討論に入ります。吉田 康一郎議員、森たかゆき議員、山本たかし議員、河合りな議員、甲田ゆり子議員、いさ哲郎議員、羽鳥だいすけ議員、小杉一男議員、石坂わたる議員から討論の通告書が提出されていますので、順次通告議員の討論を許します。 最初に、吉田 康一郎議員。 〔吉田 康一郎議員登壇〕 ○12番(吉田 康一郎) 「育児支援と防災緑地と平らな歩道の中野を創る会」、吉田 康一郎です。私からは、第12号議案、中野区人権及び多様性を尊重するまちづくり条例、そして第28号議案、中野区子どもの権利に関する条例、この二つについて反対する立場から討論をいたします。 この二つの条例の基礎となる、世界中が様々なこの人権、あるいは子どもの権利に関する法令のオリジン、起源となるのは、国連のあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約、通称、人種差別撤廃条約、そして児童の権利に関する条約、この二つが根拠となっております。そして、このあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約、ここにおきましては、この条文、これ、外務省に日本語の定訳が掲載されていますけれども、このように出ています。「世界人権宣言が、すべての人間は生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳及び権利について平等であること並びにすべての人がいかなる差別をも、特に人種、皮膚の色又は国民的出身による差別を受けることなく同宣言に掲げるすべての権利及び自由を享有することができることを宣明していることを考慮し、」と挙げ、第1条において、第1条の1項、一番最初に、「この条約において、「人種差別」とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、」こういうふうに定義され、そして2項には、「この条約は、締約国が市民と市民でない者との間に設ける区別、排除、制限又は優先については、適用しない。」このように1条の2番目に述べ、そしてさらに3項目で、「この条約のいかなる規定も、国籍、市民権又は帰化に関する締約国の法規に何ら影響を及ぼすものと解してはならない。」このように規定しています。 そしてさらに、この中で、先ほど読み上げた中で、国民的出身という言葉について、私は外務省にも確認をいたしましたけれども、まず、この外務省のホームページの人種差別撤廃条約Q&Aにはこのように書かれてあります。これも外務省の正式のホームページに記載されている事項です。「「国籍」による区別は、この条約の対象となるのですか。」という設問です。これの外務省がホームページ上で公開している回答は、「この条約上、「人種差別」とは、「人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づく」差別と定義されていることより、「国籍」による区別は対象としていないと解されます。この点については、第1条の2項において、締約国が市民としての法的地位に基づいて行う区別等については、本条約の適用外であるとの趣旨の規定が置かれたことにより、締約国が行う「国籍」の有無という法的地位に基づく異なる取扱いはこの条約の対象とはならないことが明確にされています。」このように外務省はホームページで公開し、そして、私が外務省の担当者、担当官に確認をしたところ、この国民的出身という言葉は国籍を意味しますかと、私がこのように聞いたら、それは意味しませんと。国民的というのは、例えば日本人が日本を、日本の国籍を維持している。あるいはアメリカの国籍を取得して、国籍が変わった。このような場合に、この国民的出身というのは、もともと日本人であったということを示すものだと、このように外務省では理解している。ですから、国籍による差別ではなくて、もとの出身の国に基づく差別はしてはいけませんよということであって、国籍による区別は行われるのが国際社会、国家を基本とした社会では当たり前のことであるということが外務省の説明でありました。 ところが、この第12号議案、中野区人権及び多様性を尊重するまちづくり条例、この第2条には、「全ての人が、性別、性自認、性的指向、国籍、人種、民族、文化、年齢、世代」うんたらと、「による差別を受けることなく、」とありますけれども、ここでどうして人種とか民族による差別はいけないということと同列に国籍というものを列挙して、「差別を受けることなく」と書いているのか非常に問題であります。 これは児童の権利に関する条約でも同じであります。日本も批准しているこの条約でも、「すべての人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位等によるいかなる差別もなしに」と、このように前文で掲げた上で、本論の第2条に「締約国は、」として、「児童又はその父母若しくは法定保護者の人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的、種族的若しくは社会的出身、財産、心身障害、出生又は他の地位にかかわらず、いかなる差別もなしにこの条約に定める権利を尊重し、及び確保する。」つまり、このどちらの条約にも国籍という言葉は差別してはいけませんという事例の中に入っていない。ゆえに、この児童の権利に関する条約のさらに前提となった人権条約、人種差別撤廃条約、一番の基礎のここにおいて、わざわざ第1条でこういう差別はいけないと列挙した上で、その次に大事なこととして、2項において国籍による区別は差別ではないと、わざわざ、そして3項にも同じように書いているわけであります。 この二つの条例にこの条約にない国籍に関する差別は駄目だというようなことが書いてある。そして、条約のほうには国籍による区別は差別でないというただし書きがあって、締約国のいかなる国籍に基づく異なった取扱いについても、この対象でありませんと言っていることに該当する条文がこの二つの条例にはないじゃないですか。この国籍による区別を差別だと規定して、それに対して何の説明も留保も、こういうところはそうではないと解しますよというただし書きに当たるものがない。たったこれだけの短い条例を読むだけでは、つまり、国籍による区別も差別とみなしますと、この二つの条例は規定していると読まざるを得ない。こういう立てつけの条例であります。これは大変な問題を、国際法上も国内のほかの法令との整合性からも問題を起こすことになります。 これは法律論ですが、具体的に国籍が異なることが潜在的に大きな問題を有し、引き起こすということは、日常的には認識できないかもしれませんが、国籍というのは、つまり、ある国において他の国籍であるということは、他の国家への帰属と、そこに伴う義務、これを有する法的地位の人であるということそのものでありますので、これを国内の自国の国籍の人と同じ取扱いをするということは、大きな問題が起きることは明らかであります。 例えば中国の国民は、国防動員法、国家情報法、日本と違って独裁国家ですから、海外における自国民に対しても非常に強い厳しい、場合によっては他国の利益を害するような法的義務を負わせています。あるいは、日本は国家として承認をしていない北朝鮮の国民、この人たちが国家の命令でもって、日本で拉致や工作や様々なことを行ってきて、今もその悲劇は解決をされていません。他国の国籍という法的地位を持つ、そしてその義務を負う者、これが時に戦争や侵略、工作やテロ、こういうことを引き起こすことが歴史上あまた繰り返されてきたので、国連、あるいは国際条約において、そういうことをきちんと留意して、国籍による区別、独裁国家もある、民主主義国家もある、いろんな国家がある中で、他国の国籍を持つ人をそのまま自国民と同じ扱いをすることは問題があるので、それぞれの国の国内法で違う取扱いをすることを、この条約では差別とは呼びませんと、わざわざ一番大事な定義の次の2番目に定義をしているわけであります。 現在も、ロシアがウクライナに対して行っている侵略、これも国籍という問題を抜きにして考えることはできません。この2国の歴史について長々と申し上げることはしませんけれども、一つの象徴的事例として、ロシアは近隣諸国のロシア系の住民、あるいはロシア系でない住民に対してもロシア国籍を与え、そして、その自国の国籍を持つ者だと自国民保護を名目に軍を派遣する侵略行為、あるいは他の国の秩序の破壊行為、これを繰り返すということを多用しています。 様々な昔のことではなく、現在も国籍の取扱いによって侵略行為が今まさに行われるような国際社会に置かれている日本の中野区の条例として、この国籍という問題についてぞんざいな取扱いをするこの条例は非常に問題がある。もうちょっと国籍について丁寧な取扱いをしなければ認めることはできない。このように意見を申し述べまして、反対の討論といたします。御清聴ありがとうございました。
令和4年度中野区一般会計予算
第7号議案 令和4年度中野区一般会計予算 討論 ○議長(内川和久) 次に、吉田 康一郎議員。 〔吉田 康一郎議員登壇〕 ○12番(吉田 康一郎) 育児支援と防災緑地と平らな歩道の中野を創る会、吉田 康一郎です。 まず、討論に先立ちまして、このたびのロシアのウクライナ侵略に満身の怒りをもって抗議を表明いたします。 それでは、討論に入ります。 令和4年度中野区一般会計予算に反対の立場で討論をいたします。 この反対の理由の第一は、育児支援予算であります。 日本国を構成する基礎自治体である中野区、この中野区においての一番大事な責務は何かといえば、我々の日本、我々の国が未来に存続をしていくこと、我々が先達から受け継いできたこの国、この地域を次の世代に受け継ぐことでありますので、ほかの全ての自治体と同じく我が中野区においても、次の世代を産みやすく、育てやすくして次の世代につないでいく、これが政策の一番の基礎にあると考えます。 その点において、酒井区長が、子育て先進区、これを選挙の公約の一番大事な政策として掲げ、この4年間もそれを訴えてきたことは、私もたびたび表明しているとおり賛成でありまして、そのような区政であってほしいと考えてまいりました。 しかし、1日の予算特別委員会の総括質疑において確認をしたことですけれども、この子育て先進区という区長の選挙公約について、この4年間の酒井区政で、中野区の出生率は上がるどころか23区最下位に落ちました。全国最下位に落ちたと言っても過言ではありません。 社会動態について見ても、ゼロ歳から9歳の子どもが転出超過となっている、ゼロ歳から9歳の子どもが中野からよその自治体に移っていく、このような状況が続いています。それにもかかわらず、令和4年度の子ども関係の予算が前年度よりも減少していること、そして、その減少している予算の中身が、在宅育児家庭を対象とした予算と就労育児家庭を対象とした予算に分けて比較すると、子ども1人当たりで年間180万円の差額が生じており、在宅で育児をするより子どもを預けて働いたほうが毎年180万円区の予算を多く享受できるという格差が生じ続けていること、重点プロジェクトで掲げている事業も就労育児支援に偏っており、この格差を是正するものではないことが明らかになりました。 このため、私から、子育て先進区を目指していると言うのであれば、予算も事業ももっと増やすべきではないか、そして、その中身は子ども1人当たり年間180万円も少ない在宅育児家庭への支援が含まれるべきではないか、そして、具体的な新しい施策としては、区独自の手当とか、あるいは給食費の一部無償化なども提案をいたしました。しかし、育児環境の大幅な改善や出生率の上昇や、子どもの区外流出が止まり逆に子どもが増えてくるようなことを期待できる答弁を得ることはできませんでした。 区長の子育て先進区というのは、スローガンとしてはすばらしいけれども、実態が伴っていない、中身がない。この区政、政策を続けては、中野の出生率はずっと全国最下位付近をうろつくだけ。中野の子育ては、ほかの全ての自治体よりも厳しい子育て残酷区だ、この状況が変わることはない、このように失望しています。 理由の二つ目は、中野駅新北口駅前エリアの再開発事業であります。 これまで繰り返し再考を促してまいりましたけれども、この地区について、民間事業者に売り払うのではなくて、区が土地を持ち続けて、定期借地などの制度を用いて区が持ったままでも再開発ができますよ、このようなことをお示しし、これまでいろいろな場において確認してきましたが、区は区議会に対して、事業の在り方について判断するために必要な様々な情報を示さないまま再開発の賛成だけを求め続けてきたことについて確認をいたしました。 そして、直近では、中野駅新北口駅前エリア拠点施設の容積率を、プロポーザルによる選定が終わってから、議会への説明も相談もなく900%から突然1000%に変更した。これは、プロポーザルに参加した別の事業者からしても納得が得られるものではないだろう。 そしてまた、今回の予算特別委員会で、平成17年3月制定の議会の議決すべき事件等に関する条例と、その条例に基づき平成20年10月に定めたサンプラザ地区に係るまちづくり整備の方針についての「3.中野区は、株式会社まちづくり中野21に「区役所・サンプラザエリア」周辺一体のまちづくりの中心として主体的に取り組ませるものとする。」「4.中野区は、株式会社まちづくり中野21日に将来にわたって同社の所有地を保有させ、中野駅周辺のまちづくりをけん引させるものとする。」に反して土地の保有を含めた基本協定書を野村不動産と締結したことは問題ではないかとの指摘がありました。 提案されている令和4年度一般会計予算は、様々な問題を含んでいる現在の事業を何の改善もなく進める予算となっています。このような予算を承認しては、この中野駅北口、手放したら二度と区が取り戻すことはできない土地について、そして、手放さなくても再開発ができる、このような状況が整っているにもかかわらずこれを手放してしまうということを座視することになる。このような予算に賛成することはできません。 その他の様々な事業についての予算には賛成できることも多々あるということを申し述べて、私の反対の討論を終わります。 御清聴ありがとうございました。 ○議長(内川和久) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。
令和4年度中野区一般会計予算案について
令和4年度中野区一般会計予算案について 総括質疑 ○ひやま委員長 次に、吉田 康一郎委員、質疑をどうぞ。 ○吉田 委員 育児支援と防災緑地と平らな歩道の中野を創る会、吉田 康一郎です。ラストバッターです。よろしくお願いいたします。 まず最初に、育児支援政策について伺います。 在宅育児支援に焦点を絞ってお聞きします。区が昨年9月に策定した中野区基本計画の重点プロジェクトで掲げている施策は、働きながら育児をする家庭の支援に関する事業が大部分であり、在宅で育児をしている家庭への支援があまりありません。一部に、在宅育児家庭も利用できる相談事業、あるいは環境整備などが掲げられているだけであります。私の一般質問に対する答弁で、過去3年間の子ども関連予算の新規、拡充・推進事業の規模が約618億円、廃止事業は約768万円とありました。その中身は、学校再編に伴う施設整備などを除くと、予算額の大きなものから、令和元年度の認可保育施設新規開設支援、建て替え支援、そして次に、令和3年度の区立保育園民営化、民間保育施設新規開設支援、次が令和元年度の区立保育園民営化などであり、やはり就労家庭支援が大部分で、在宅育児家庭の支援があまりありません。 そこで、区の育児関連予算を在宅育児支援と就労家庭支援に係る経費に振り分け、比較した場合、子ども1人当たりに換算すると、それぞれの区の支援の金額は幾らになるのか、伺います。 ○青木子ども政策担当課長 区では、在宅育児家庭に限定したサービス等は行っておらず、在宅育児家庭も含め、広く子育て家庭を対象として、子ども・子育て支援のサービスを実施しているところでございます。一方で、未就学児のいる就労家庭におきましては、保育サービスを提供しているところでございまして、保育サービスに係る経費を利用している子ども1人当たりで割り返すと、令和2年度決算額でおよそ年額約230万円でございます。なお、幼稚園につきましては、東京都が幼稚園に直接交付している助成金を除き、年額52万円でございます。 ○吉田 委員 つまり、多くのサービスは、就労家庭、あるいは在宅で育児する家庭、両方に係るけれども、在宅の家庭に係るものが大体50万円ぐらい、幼稚園関係、そして就労家庭は保育園などがメインだと思うんですけれども、230万円の区の予算が投じられている。すると、この差は毎年1人当たり180万円の差が生じていると。在宅で育児をしようとするよりも、働いて子どもを預けちゃったほうが毎年180万円、区の支援としてはお得だということであります。これは働き方、あるいは育児の仕方に対して、平等、公平ではない。経済的にある働き方、やり方をインセンティブを与えてしまっている。ほかのやり方にディスインセンティブを与えてしまっているということであります。 私は、常々、育児支援政策は、欧州諸国などと同様、育児環境整備だけでなくて、直接経済的支援を行うべきだとして、お聞きしてまいりました。この180万円も毎年子ども1人当たり、2人いれば360万円、3人いれば540万円ですが、これだけ差が出てしまう。これについて、在宅育児家庭にも、就労育児家庭にも公平に経済的な支援を区は実施すべきだと考えますが、見解を伺います。 ○青木子ども政策担当課長 就労家庭のみでなく、在宅育児家庭に対しても、子ども・子育て支援のサービスを提供し、適切に支援していくという視点が重要であると認識しております。経済的な支援につきましては、その効果や公平性、財政負担などを総合的に勘案していく必要がございまして、今後、他自治体の取組等を研究してまいりたいと考えてございます。 ○吉田 委員 理念的には、そういう御答弁いただいてうれしいんですけども、現実はそういう予算になっていないわけですよね。この180万円の差額、この何割かの金額でも、例えば在宅の育児の家庭に手当として給付すれば、それだけ在宅で手当がもらえるなら、保育園に預けずに在宅で子どもを育てようという家庭も増えて、子どもにもよい環境、育児環境を与えられるとともに、区の財政面でも、要するにゼロ歳児保育をやると、区は1人当たり40万円払うわけですよ。それを20万円、例えば――これは極端ですけど、「20万円あげるから」って言ったら、「じゃ、20万円も毎月もらえるんだったら、保育園に預けるのをやめて、1年間ちゃんと育児休暇取ろうかな」とか、「3年間取ろうかな」、結局、保育園に行く人が減って、自宅で育てるという人も増えるという可能性もあると思います。ぜひ、育児に関して、預けちゃったほうが得だと、こういう癖をやめていただきたいと思います。 次に、子どもの施設について伺います。 プレーパークについて、重点プロジェクトに入っていますけれども、現在は上高田で出張プレーパークを行っているのみであります。常設のものを北部、中部、南部と、3か所はあってほしいものだと私は思っています。キッズ・プラザは、中野区は学校内につくろうとしていますけれども、都の補助金は学校内につくらなくても受けることができる制度と理解しています。区は、児童館を中学校区に1館ずつと考えているようですけれども、これを児童館やプレーパークを含めた子どもの居場所施設を広く捉えて、全体としてそれぞれ小学校区に1個ずつあるよと、こういうような方針を打ち出したほうがいいのではないか、このように思いますが、これ、なかなか一生懸命提案しても変わらないようなので、これ答弁を求めないで、意見にとどめまして、プレーパークの事業についての今後の方針についてのみ伺います。 ○細野育成活動推進課長 プレーパークについてお答えいたします。プレーパークについては、様々な支援策を講じることで各地域での展開につなげていきたい、このように考えているところでございます。 ○吉田 委員 ぜひ柔軟に考えていただきたいと思うんですが。 次に、給食費について伺います。 フィンランドやスウェーデンでは、小・中学校の給食は無償です。イギリスでは、小学校1、2年生の学校給食が無償だということです。我が国では、全国1,740の自治体のうち76の自治体で小中学校とも無償化、424自治体の一部無償化、一部補助を実施しています。そして、その数は少しずつ増えているとのことであります。中野区内の全小学校、全中学校、あるいは全小・中学校の給食費を無料にしようとすると、今よりも増える経費は幾らでしょうか。 ○松原学校教育課長 令和3年度の全児童・生徒数を基に、給食費の平均で概算をいたしましたところ、既に負担をしている就学援助認定者を除きまして、新たに負担をする経費は、年間で小学校が4億7,900万円ほど、中学校で1億6,700万円ほど、合計6億4,600万円ほどとなってございます。 ○吉田 委員 まずは、例えば小学校だけ、あるいは英国のように1、2年生だけ無償化する、こういうことは考えられませんか。 ○松原学校教育課長 就学援助制度によりまして、必要とされる世帯への支援はなされているというふうに考えてはございます。その他の取組につきましては、今後も研究をしてまいりたいと考えております。 ○吉田 委員 研究してください。 今回の資料要求で、中野区の最新の合計特殊出生率が出ました。0.97であります。これまでずっと、るる申し上げてきたとおり、平成29年に1.04、平成30年に1.00、そして令和元年に0.93と、酒井区政になってから、どんどん23区内の出生率の順番が下がって、びりになったわけですけれども、とうとう最新に0.93が0.97、少し改善したわけであります。その前の年の1.00には届かなかった。道半ばというよりも、2歩後退した後で、半歩だけ前進したと、こういう状態であります。23区内の順位はまだ公表されていないということですが、これが改善していることを祈るばかりであります。 新年度の子ども関係の予算は、前年度よりも減少しています。子育て先進区ということを常に目指すと、目指しているというのであれば、予算も、事業ももっと増やすべきではないんでしょうか。そして、その中身は、区の予算が180万円も、育て方によって差がある。預けると180万円得、自宅で育てると180万円、1人につき損、こういう格差を生じさせるような事業、これについて少しでも、在宅の方も同じ金額の税金を払っているんだから、同じだけサービスが区からもらえるように、こういう新しい事業を考えるべきではないでしょうか。 そして、そのような施策を携えて、出生率ということに何とか目標から取ろう、取ろうと、今度の基本計画でも、結局、出生率を上げなきゃいけないとだけ言ったけれども、数値目標をほかの自治体と違って掲げない、こういうことをやってきましたけれども、ほかの多くの自治体と同じように、自信を持って、施策の裏付けをもって、出生率の目標を掲げるべきではないかと思います。今年度よりも少ない予算の新年度予算、そして事業も従来と同じような事業、こういうことじゃなくて、新しく本当に先進区を目指すと、言葉だけではなくて、中身も納得できるような施策と予算を求めますが、区長の見解を求めます。 ○酒井区長 子どもの関係の予算につきましては、年度ごとの臨時的な経費も含まれておりますので、我々としては子育て先進区を目指す中で、予算的には拡充を基本的な姿勢として取り組んでいるところでございます。合計特殊出生率につきましては、目標として掲げること自体は難しいとは考えておりますけれども、我々としては、当然、子育て先進区を取り組み、結果としてそこが向上することを望んでおるところでございます。 ○吉田 委員 前の田中区長のときは、頑張って1.26っていう目標を掲げていたんですよ、できるできないは別にして。予算も減らして、あるいは在宅で育てていると損をする。こんなことを、新年度の事業を見ても、やっぱり就労家庭にのみ、新しい事業は偏っていく。私は大変申し訳ないんですが、今の区長の考え方、方針、予算のつくり方、こういうことではいつまでたっても子育て先進区にはならない。中野はいつまでたっても、ほかの区に比べて、出生率が上がって子育てしやすい区になるとは到底思えません。今の方針を変えていただかない限り、今の予算を変えていただかない限り、到底区長の公約は達成できるとは思いません。 次に、水と緑のまちづくりについて伺います。 1人当たり公園面積が23区で下から2番目である我々中野区では、水と緑のまちづくりは特に重要であります。一般質問で、水や水辺を生かしたまちづくりの必要性について伺って、一つの切り口として、区内の池や沼、湧き水などの水辺がどれだけあるか、伺いました。今回、新規に資料要求を行いまして、区内の公園で、池などがある公園は、新井薬師公園、哲学堂公園、紅葉山公園など9か所、名称と場所が分かりました。区内の池とか湧き水などについて、網羅的に調べて一覧表を示していただいたのは初めてだと思うんですが、そうでしょうか。 そして、それぞれの公園の池には名称がある池、ない池があるとのことです。そしてまた、面積や水深などの状況も把握していないということです。今後、こういうことはきちんと、区の管理する公園ですから、調査し公表すべきと考えますが、見解を伺います。 ○林公園緑地課長 水辺のある公園として取りまとめた一覧表を作成したのは、今回が初めてでございます。今後、池などの面積や水深等について、資料や現地の調査を行い、ホームページなどでの公表を検討してまいりたいと考えているところでございます。 […]
1育児支援政策について 2緑と水のまちづくりについて 3国民保護施策について 4人権行政について 5自治施策について 6その他
一般質問 中野区議会議員 吉 田 康一郎 1 育児支援政策について 2 緑と水のまちづくりについて 3 国民保護施策について 4 人権行政について 5 自治施策について 6 その他 ○議長(内川和久) 次に、吉田 康一郎議員。 〔吉田 康一郎議員登壇〕 ○12番(吉田 康一郎) 育児支援と防災緑地と平らな歩道の中野を創る会、吉田 康一郎です。よろしくお願いいたします。 まず育児支援政策について伺います。 昨年9月に区が策定した中野区基本計画において、私が繰り返し指摘した出生率の向上を図ることが盛り込まれました。この出生率の向上について、なかなか記載すらしようとしなかったという過程について理解に苦しんでいましたけれども、実際に中野区の過去3年間の出生率を調べると、過去の定例会で申し上げたとおり、平成29年に23区内で豊島区と同率で下から2番目、翌平成30年は単独で最下位から2番目、そして令和元年では単独最下位になりました。酒井区政になってから子育て先進区を掲げていながら、出生率はどんどん下落し、順位も下落し、最下位になったわけであります。そして、社会動態については、0歳から9歳については転出が超過、区外に出て行く人が多いとなっています。 経済紙系の調査で、2021年版「共働き子育てしやすい街ランキング」で6位になったと指摘する向きもありますが、それはあくまで共働きのランキングであって、子育て世帯全体の評価ではない上に、実際の出生率とその順位が下落しているのに、子育てしやすいというのは、使いにくい商品の売上げが落ちているのに顧客満足度ナンバーワンと宣伝しているようなものです。 これまで3年半の区政について、出生率が下がって、結果として子育て後退区になったというのにもかかわらず、10日の施政方針演説においては、この点についての反省は一切ありませんでした。これまでの施策が失敗であったということを認め、それを転換する、こういうことがなければ未来において子育て先進区ということは実現できません。 令和4年度予算において子育て支援の中心を担っている子ども教育部では、出生率の向上に向けてどのような事業を実施する予定なのか。それはこれまでと同じなのか。変わるのか。新規、拡充、廃止によって、これまでの事業の継続と比較して、出生率が何ポイント向上する見込みなのか。そして子ども関係の予算は令和3年度よりも減少しているけれども、これは事業も予算も拡充すべきなのではないか。そして、これまで繰り返し指摘しましたが、我が国の育児関連政策は、フランスや北欧などに比べて育児世帯への手当の支給が極めて低い。国の児童手当と別に区として手当金を支給するなど思い切った施策が必要だと考えますが、見解を伺います。 次に、産後ケアについて伺います。2月4日の読売新聞に「妊産婦孤立させない 中野の助産院拡大移転へ 来院殺到 安らげる場所に」という記事が掲載されました。概要は、「新型コロナウイルス感染拡大による母親学級の休止・縮小などの影響で、出産や子育てに不安を募らせる妊産婦が増えている。中野区のしらさぎふれあい助産院には昨年暮れ頃から、相談に訪れる妊産婦たちが殺到。支援体制を整えようと、近くの施設に拡大移転することを決めた」という内容で、私も院長にお話を伺いましたが、現在クラウドファンディングで整備費を募っているとのことです。 自治体の産後ケア事業を受託している施設の修繕等に対する国・都の補助制度として、妊娠・出産包括支援緊急整備事業がありますが、この制度は区市町村や委託先の施設が所有している施設が対象で、賃貸で運営している施設は対象となっていません。中野区は、この補助事業を活用した事業を実施していないと聞きます。 そこで伺います。都内でこの制度を活用した事業を実施している市や区はあるのでしょうか。 そして次に、区内の産後ケアを行う施設に対して、国や都の制度を活用できない場合でも、中野区が子育て先進区を標榜するのであれば、このような助産院などを支援する事業を行うべきではないんでしょうか。中野区は南部で施設の整備を検討しているやに伺っていますが、北部においても、この助産院を含め支援の検討を行うべきと考えます。また、国や都に対して、賃貸で運営している施設に対しても補助できる制度の整備を働きかけるべきであると思いますが、見解を伺います。 次に、緑と水のまちづくりについて伺います。 これまで私は、中野区には公園面積が非常に少ないことが問題であることを繰り返し指摘し、1人当たりの公園面積が23区内で下から2番目、緑豊かな公園やオープンスペースを増やし、人々が憩え安らぎを持てる空間づくりが大事だと要望してまいりました。そして緑とともに重要なのは、水辺のある空間であります。水辺は人々に潤いと憩いを与え、良好な都市景観を形成する上でも極めて重要な要素であります。魅力ある水辺空間、さらには多様な生物の生息できる環境に配慮したまちづくりを積極的に進めることが、魅力と価値を格段に高める都市形成になっていくことは言うまでもありません。 そこで伺います。区内の公園で池や湧き水、噴水など水辺を生かした公園は幾つあるのか。具体的に公園の名称を挙げていただきたい。 次に、公園以外の、例えば昔から自然に湧き水が出ている水辺や池、沼などが現在の中野にどれだけあるのか伺います。神社仏閣などにあるものは、一部私、思い浮かびますけれども、例えば観光資源や歴史的資源として区内にどれだけあるのか、区は把握しているのか伺います。そして把握していないのであれば、これからは把握し、公表すべきであると思いますが、見解を伺います。 さらに、こうした緑や水を生かしたまちづくりについて、改定中の都市計画マスタープランでは、どのような方針を盛り込んでいるのか伺います。この水辺空間を生かしたまちづくりを積極的に進めることを強く要望します。 次に、人権行政について伺います。 去る2月1日、衆議院において「新疆ウイグル等における深刻な人権状況に対する決議」が可決されました。参議院も北京五輪後に決議採択を目指しているとのことであります。共産党独裁体制下の中国の新疆ウイグル、チベット、南モンゴルなどにおけるジェノサイド、これについては多くの国が中国への非難と制裁を始めています。そして、北京五輪についても多くの国がボイコットを行い、我が国も事実上の外交ボイコットを行いました。このような中、我が中野区が北京市西城区との友好事業を行うことは、中野区が中国政府のジェノサイドを問題視しないと表明するに等しい行為です。西城区はその区内に人民大会堂など中国の政府、共産党、軍の重要機関が密集し、中国共産党高級幹部専用住宅街である中南海などが位置し、まさに中国共産党独裁の中枢であり、人権侵害政策の中枢であります。 私は昨年12月20日、竹村あきひろ区議とともに、このような趣旨でこの友好区35周年行事の中止を申し入れましたが、区長は行事を行ったようであり、残念に思います。今年は日中国交樹立50周年に当たりますが、到底これを祝うような状況にはありません。中国独裁の人権状況について、そして我が国国会の決議について、区長の見解を伺います。 そして次に、北朝鮮拉致問題です。北朝鮮人権侵害週間には、昨年も人権週間と重なる期間のみポスター掲示を行い、そして一つよかったことは区のホームページに、「12月10日から16日は北朝鮮人権侵害問題啓発週間です」と題するページを作りました。これは国や都のページともリンクを張るなどいい内容でありましたが、なぜか今は影も形もなくなっています。現在、区のホームページの人権啓発活動というページを見ると、人権週間については詳しくコンテンツが掲載されていますが、北朝鮮拉致問題については1件も掲載されていません。そして「北朝鮮」と検索しても、拉致問題について1件もヒットしない。気持ち悪さすら感じました。北朝鮮人権法に定められた自治体の責務、これは拉致問題が解決するまで、北朝鮮に拉致された国民の最後の一人が帰ってくるまで恒常的に掲示、啓発を続けることが責務となっているのではないでしょうか。見解を伺います。 自治体によっては、幹部職員にブルーリボンバッジの着用が呼びかけられ、全幹部職員が着用している自治体もあります。区長の人権に対する認識が偏り、そして低過ぎると思います。ぜひこのジェノサイドなどの問題、あるいは北朝鮮拉致問題、このような問題について積極的に区としても広報や啓発を行うべきと考えます。令和4年度予算に盛り込んだものは何なのか見解を伺います。 そして啓発に当たっては、これは昨年の第4回定例会で伺いましたが、時間切れで答弁をいただけなかったので改めて伺いますが、中野駅ガード下ギャラリーの壁が老朽化しており、掲示効果を低下させています。ここを塗装や改修、補修など壁面の改修を行い、そしてこの啓発事業を行うべきだと考えますが、見解を伺います。 最後に、町会・自治会の支援について伺います。 中野区は、区内の町会・自治会、そして町会連合会に対し、長年にわたり防災や防犯、交通安全、福祉活動、古紙の集団回収など、様々な地域の公益活動を依頼し、協力を得ています。改めて頭の下がる思いであります。しかし、武漢から始まった新型ウイルス感染症により、活動の抑制、縮小を余儀なくされ、その状況が長引くにつれ、活動の再開と活性化に苦心、苦労する状態になっている町会の活動に対し、区が評価し、再開を期待していることを示す意味からも、財政的支援があれば激励されるとの要望をお聞きします。このような新たな財政的支援措置を検討すべきと考えますが、見解を伺い、全ての質問を終わります。御清聴ありがとうございました。 〔区長酒井直人登壇〕 ○区長(酒井直人) 吉田 議員の御質問にお答えします。 まず最初に、令和4年度予算における育児支援政策についての取組についてです。 令和4年度予算におきましては、子どものセーフティネットを強化するとともに、子育て・子育ち環境や地域全体で子育てを応援するための体制の整備に向けた予算案を編成しております。具体的には、(仮称)中野区子どもの権利に関する条例に基づく救済機関などの設置、教育相談体制の充実、子どもの貧困対策の推進、児童相談所の設置及び子ども・若者支援センター等運営、児童館での一時預かり、ベビーシッター利用支援など実施を予定しております。こうした事業の実施を通じて、中野区基本計画の重点プロジェクトの一つである子育て先進区の実現を図ってまいります。 次に、合計特殊出生率の向上についてでございます。区は、基本計画において、子育て家庭の定住を促進していくために、子ども女性比の増加を目指すことを掲げております。近年、区の子ども女性比は横ばいから減少の傾向にあることから、今後は増加傾向に転じていくことを目指し、安心して子どもを産み、育て、住み続けられる環境の整備を進めてまいります。 次に、子ども関連予算の拡充についてでございます。令和4年度の予算案におきましては、基本計画で掲げる重点プロジェクトなどを重点事項とし、限られた財源を優先的に配分し、子育てや教育関連などの施策を強く推進していくための予算を計上したところであります。今後は、基本計画で示す重点プロジェクトに基づき、子ども関連施策のさらなる充実を図ってまいります。 過去の子どもの関連施策と現金給付についてでございます。過去3年間の子ども関連予算では、様々な新規拡充推進事業に取り組んでいるところでございまして、令和元年度から令和3年度までの3か年で、新規拡充推進事業は74件、予算ベース約618億円、一方、廃止した事業件数は1件で768万円でございます。一律の現金給付などの経済的支援につきましては、その効果や公平性、財政負担などを総合的に勘案していく必要がありまして、今後他自治体の取組等も研究してまいります。 次に、国・都の補助制度活用による産後ケア施設の修繕事例についてでございます。令和3年度に三鷹市と府中市において、妊娠・出産包括支援緊急整備事業を活用した施設の修繕等を実施しており、いずれも委託先の法人が所有している施設の一部改修工事であると聞いております。 次に、施設整備に関する補助制度の検討と要望についてでございます。産後ケア事業を行う施設については、区内における偏在の解消を含め、適切なサービス提供を図ることができるよう、どのような支援が可能か検討を進める考えでございます。また、施設整備に関する補助制度の充実につきましては、賃貸物件も補助対象となるよう、国や都へも働きかけてまいります。 次に、緑と水のまちづくりについて、区内の池や噴水を生かした公園についてで、じゃぶじゃぶ池を除き、池や噴水などがある区立公園は、新井薬師公園、哲学堂公園、紅葉山公園など9公園ございます。 次に、区内の池や沼の把握についてでございます。民有地について、例えば大和町の蓮華寺の池など公開されているものは一定程度把握しているところであります。 次に、都市計画マスタープランと緑と水のまちづくりでございます。改定中の都市計画マスタープランでは、基本的な都市構造として、まちを守り、うるおいを生み出すグリーンインフラの育成強化を図ることとしております。この中で、みどりと防災の環境軸、水とみどりの親水軸の形成など、緑や水辺を生かした都市整備の在り方を示しております。 次に、人権行政についてで、衆議院における新疆ウイグル自治区等の人権状況に対する決議についてです。衆議院において人権状況に対する決議が行われたことは承知をしております。国からの正式見解はまだ示されておりませんが、政府の今後の動向を注視していきたいと考えております。 最後に、北京市西城区との交流についてでございます。北京市西城区とは、1986年の友好区関係締結以降、行政間交流のほかに文化の分野では書道や茶文化など、スポーツの分野では少年軟式野球などを通じた民間レベルでの交流がこれまで行われてきたところであります。昨年12月には、友好区関係締結35周年記念交流事業をオンラインで実施し、その中で友好関係の継続発展に関する覚書を交わしたところでありまして、今後も引き続き交流関係を継続してまいります。 […]
令和2年度中野区一般会計歳入歳出決算の認定について
議案 認定第1号 令和2年度中野区一般会計歳入歳出決算の認定について 討論 ○議長(内川和久) これより討論に入ります。吉田 康一郎議員、山本たかし議員、南かつひこ議員、羽鳥だいすけ議員、渡辺たけし議員、石坂わたる議員から討論の通告書が提出されていますので、順次、通告議員の討論を許します。 最初に、吉田 康一郎議員。 〔吉田 康一郎議員登壇〕 ○12番(吉田 康一郎) 育児支援と防災緑地と平らな歩道の中野を創る会、吉田 康一郎です。よろしくお願いいたします。 令和2年度中野区一般会計歳入歳出決算の認定について、反対の立場で討論を行います。 理由の第1は、育児支援政策にあります。先月24日の決算特別委員会の総括質疑において、中野区の過去3年間の合計特殊出生率を伺ったところ、平成29年1.04、平成30年1.00、令和元年0.93と3年連続で下がったとの説明がありました。その質疑において、質疑の前日に放映されたテレビ東京の「ワールドビジネスサテライト」というニュース番組で報じていた関東近県の自治体の出生率を紹介いたしましたが、基準年が若干異なっているところがありましたので、改めて、東京都が昨2020年12月1日に公表した、すなわち最新の報告であります「令和元年(2019年)東京都人口動態統計年報(確定数)」を調べますと、平成29年から令和元年にかけては、東京都全体として見ても出生率1.21から1.15に0.06ポイント低下しています。 しかし、中野区は、もともと低い1.04から0.93と0.11ポイント、すなわち東京都全体の倍近く下がっております。この結果、23区での順位は、平成29年、豊島区と同率で最下位から2番目、平成30年、単独で最下位から2番目、そして令和元年、単独最下位と順位でも下落し、出生率の数値自体の低下には一定の理解ができるとしても、「子育て先進区」を掲げる酒井区政になってから、都内23区26市で最下位に下落いたしました。 そして、中野区の出生率が1を割った令和元年でも、23区で出生率1.3を超える自治体が中央区、港区、江戸川区の3区、1.2を超える自治体は千代田区、荒川区、葛飾区、江東区の4区あります。もちろん26市の平均はもっと高いわけです。 私が予算の審議に当たって、あるいは中野区基本構想や基本計画の策定に当たって、子ども文教委員会において、様々な議会の場において、育児政策に関わる根本的な指標である出生率を基本に据えた上で、エビデンスに基づく政策の実施を求めてきたことを受け止めず、3年間行ってきた区政の結果がこれであります。 次に、決算の認定に反対する理由の二つ目、中野駅新北口駅前エリア(区役所・サンプラザ地区)の再開発事業であります。本年3月の第1回定例会における令和3年度中野区一般会計予算案に対する審議を含め、これまで様々な場で申し上げてきたとおり、区は、区議会に対して重要な数値を全く示さないで今に至るまま、議会の賛成を求め続けてきました。これは、予算特別委員会などこれまでの議会で確認をした事実であります。 まず、定期借地制度、豊島区やほかの区で行っている70年定借などの方式と、土地を売ってしまう、この選択に当たって金額、数値を区議会に示さず、定借という方式は無理だという雰囲気だけをにおわせて、区議会に対し、土地を売ってしまう方式による再開発の計画をどんどん進め、承認を求め続けてきました。 一昨年12月の中野駅周辺整備・都市観光調査特別委員会において、多くの議員が定借制度により得られる前払い地代の算定を区に繰り返し求めたところ、ようやくそれまで一切出さなかった数字を出しましたけれども、それは、区役所の整備費は254億円かかるが、前払い地代は180億円しか得られないという全く誤った金額でありました。算定根拠を聞くと、租税公課だけを算定し、期待収益率を0と置くという、正規の不動産鑑定の方法ではあり得ない算定でありました。 これについては議員有志が日本最大手の不動産鑑定会社に調査を依頼し、ホテルやアリーナなど採算性の低い事業を組み込んでもなお、少なくとも約600億円の前払い地代が得られるとの結果を得て、これを区に提出し、区として正規の不動産鑑定を行うよう求めましたけれども、これを行わず、土地を売り払う開発計画を進め、しかし、議会の要望により、プロポーザルに応じた企業に対し、区が土地を保有する形で事業を行うケースについても考え方を示すよう求めることとなりました。 ところが、今年3月2日の予算特別委員会での選定候補事業者に関する報告の際にもその結果を示しません。選定候補事業者となった野村不動産が従前資産を令和元年の路線価で560億円と評価したということも、私がこの計算で合っていますねと聞き、その計算で合っていると思いますと、こういう形でようやく議会に数字を示しました。 落選した東京建物は、野村不動産より100億円多く従前資産を上積みして算定していました。令和2年、中野区の駅前の土地は15%地価が増加しており、100億円多く区の財産を算定してくれて、それだけの評価をしても事業の採算が取れると、その能力を示しました。これについても、中野駅周辺整備・都市観光調査特別委員会では説明がなく、予算特別委員会で執拗に質問した結果、ようやく公表しました。 議会に対して、議会が判断する際に重要な事項であっても、区は適正な調査をしない、数字を示すということをしない、こういう予算の執行でありました。適正であったと認定することはできません。その他の様々な事業についての決算には賛成であるということを申し述べて、反対の討論といたします。ありがとうございました。