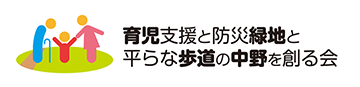カテゴリ:facebooklog
2014/08/18 8:35
産経新聞、「吉田調書」入手。朝日新聞の「原発 命令違反し9割撤退」記事が捏造である事、菅直人元総理大臣の「東電が全面撤退しようとした」が嘘であり、菅氏の指示が現場の混乱を招いていた事が明らかに。 — 《【吉田調書】吉田所長、「全面撤退」明確に否定 福島第1原発事故》 2014.08.18 産経新聞 平成23年3月の東京電力福島第1原発事故に関し、産経新聞は17日、政府の事故調査・検証委員会が事故発生時に所長として対応に当たった吉田昌郎氏(25年7月9日死去)に聞き取り調査してまとめた「聴取結果書」(吉田調書)を入手した。吉田氏は東電が事故発生3日後の14日から15日にかけて第1原発から「全面撤退」しようとしていたとする菅直人首相(当時)らの主張を強く否定し、官邸からの電話指示が混乱を招いた実態を証言している。吉田氏は一方で、現場にとどまった所員には感謝を示すなど、極限状態での手探りの事故対応の様子を生々しく語っている。 吉田氏への聴取は23年7月から11月にかけ、事故収束作業の拠点であるサッカー施設「Jヴィレッジ」と第1原発免震重要棟で計13回、延べ27時間以上にわたり行われた。吉田調書はA4判で約400ページに及ぶ。 それによると、吉田氏は聴取担当者の「例えば、(東電)本店から、全員逃げろとか、そういう話は」との質問に「全くない」と明確に否定した。細野豪志首相補佐官(当時)に事前に電話し「(事務関係者ら)関係ない人は退避させる必要があると私は考えています。今、そういう準備もしています」と話したことも明かした。 特に、東電の全面撤退を疑い、15日早朝に東電本店に乗り込んで「撤退したら東電は百パーセント潰れる」と怒鳴った菅氏に対する評価は手厳しい。吉田氏は「『撤退』みたいな言葉は、菅氏が言ったのか、誰が言ったのか知りませんけれども、そんな言葉を使うわけがない」などと、菅氏を批判している。 朝日新聞は、吉田調書を基に5月20日付朝刊で「所長命令に違反 原発撤退」「福島第1 所員の9割」と書き、23年3月15日朝に第1原発にいた所員の9割に当たる約650人が吉田氏の待機命令に違反し、10キロ南の福島第2原発へ撤退していたと指摘している。 ところが実際に調書を読むと、吉田氏は「伝言ゲーム」による指示の混乱について語ってはいるが、所員らが自身の命令に反して撤退したとの認識は示していない。 また、「退避」は指示しているものの「待機」を命じてはいない。反対に質問者が「すぐに何かをしなければいけないという人以外はとりあえず一旦」と尋ねると、吉田氏が「2F(第2原発)とか、そういうところに退避していただく」と答える場面は出てくる。 http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140818/plc14081805000001-n1.htm — 《【吉田調書】「あのおっさんに発言する権利があるんですか」 吉田所長、菅元首相に強い憤り》 2014.08.18 産経新聞 「私にとって吉田(昌郎)さんは『戦友』でした。現(安倍)政権はこの(吉田)調書を非公開としていますが、これは特定秘密にも該当しないし、全面的に公開されるべきです」 菅直人元首相は月刊宝島8月号で、ジャーナリスト(元朝日新聞記者)の山田厚史氏のインタビューに対し、東電福島第1原発の元所長、吉田氏を自らの「戦友」だと述べている。 だが、産経新聞が入手した吉田調書を読むと、吉田氏側は菅氏のことを「戦友」とは見ていない。むしろ、現場を混乱させたその言動に強い憤りを覚えていたことが分かる。 例えば、政府事故調査・検証委員会の平成23年11月6日の聴取では、「菅さんが自分が東電が逃げるのを止めたんだみたいな(ことを言っていたが)」と聞かれてこう答えている。 「(首相を)辞めた途端に。あのおっさんがそんなのを発言する権利があるんですか」 「あのおっさんだって事故調の調査対象でしょう。辞めて、自分だけの考えをテレビで言うというのはアンフェアも限りない」 菅氏は同年8月の首相辞任後、産経新聞を除く新聞各紙やテレビ番組のインタビューに次々と応じ、自身の事故対応を正当化する発言を繰り返していた。これを吉田氏が批判的に見ていたことがうかがえる。 また、菅氏が自分も政府事故調の「被告」と述べていたことから、吉田氏は「被告がべらべらしゃべるんじゃない」とも指摘し、事故調が菅氏に注意すべきだとの意見を表明した。 菅氏だけでなく、当時の海江田万里経済産業相や細野豪志首相補佐官ら菅政権の中枢にいる政治家たちが、東電が全面撤退する意向だと考えていたことに対しては「アホみたいな国のアホみたいな政治家」とばっさり切り捨てている。 その菅氏は今年7月24日付のツイッターで、吉田調書についてこう書いた。 「吉田調書など(で)当時の状況が明らかになり、発生翌朝現地で吉田所長から話を聞き、撤退問題で東電本店に行った事も理解が増えています」 吉田氏の肉声はこれとは食い違う。政府事故調の聴取(23年7月22日)で「(菅氏は)何のために来るということだったんですか」と質問され、こう突き放している。 「知りません」 「行くよという話しかこちらはもらっていません」 さらに必死で作業を続けている所員らに菅氏が激励もせずに帰っていったことを証言している。 菅氏が震災発生4日後の15日早朝、東電本店に乗り込んだことにも冷ややかだ。同じ頃、現場でまさに死と向き合っていた吉田氏は7月29日の聴取で、テレビ会話を通してみた菅氏の東電本店での叱責演説についてこう語っている。 「ほとんど何をしゃべったか分からないですけれども、気分悪かったことだけ覚えています」 「何か喚いていらっしゃるうちに、この事象(2号機で大きな衝撃音、4号機が水素爆発)になってしまった」 http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140818/plc14081805000002-n1.htm
2014/08/18 7:19
中国の中距離ミサイル増強に、ロシアは中距離核戦力全廃条約(INF条約)の故に対抗できず。米国も同じ悩み。米露が同条約を離脱となれば、アジアの戦略環境は一変。ここでも中国の軍拡が、世界の軍縮の流れを逆転させています。備えるしかありません。 — 《アジアの地政学を一変させるロシアのINF条約違反 米国も中距離ミサイル配備で中国に対抗か?》 2014.08.18 福田 潤一 金門島の歴史的経験を題材に離島防衛のあり方を論じた「中国の侵攻を撥ねつけてきた台湾の小さな島 金門島に学ぶ国境離島を防衛する方法」(7月25日)に引き続き、今回も抑止と防衛にかかわるトピックを取り上げたい。7月末に米国が公式に断定した、ロシアの中距離核戦力(INF: Intermediate-range Nuclear Forces)全廃条約(以下、INF条約)への違反を巡る戦略論争についてである。 「ニューヨーク・タイムズ」(NYT)紙の報道によれば、オバマ政権は7月28日、ロシアがINF条約に違反する地上発射型巡航ミサイルの試験を行っていると断定した。オバマ政権はその事実を翌日公表した国務省の報告書で明らかにするとともに、プーチン大統領に書簡を送り、米ロ間の協議開催を要請した。オバマ政権は2008年1月、ロシアのINF条約違反について、NATOをはじめとする同盟国への通告を行っていた。 この話、実は欧州のみならずアジアの戦略環境をも一変させかねない重大性を持つ。米国のみならず、日本自身も当事者と言ってよい話なのだ。しかし、どうも日本での注目がいま一つ弱いように思う。この問題がグローバルな戦略観の下でまだ十分に認識されていないのかもしれない。 仮にロシアがINF条約から脱退して再びINFを保有するようになれば、その矛先は欧州のみならず日本や中国にも向けられる。このことがまず、当然ながら重大だ。ところが、影響はそれだけに留まらない。仮にロシアがINF条約から離脱するとすれば、米国ももはやそうした条約に拘束される必要はなくなるのである。 このことは、米国が新たにINF相当のミサイルを開発・配備できるようになることを意味する。日米が中国に対して通常弾頭型の中距離/準中距離の弾道ミサイル配備において劣勢に置かれている現状を勘案すれば、INF条約の廃止はそうした劣勢を打開するチャンスになるかもしれない。 いずれにしても、ロシアのINF条約違反は、アジアの戦略関係を根本から変化させかねない重大性を持つ話なのである。 ■ INF条約とは何か まずINF条約とは何かを振り返っておきたい。これは、1987年12月に米ソ間で締結された、中距離核戦力(INF)の全廃条約である。INFとは何かと言うと、射程500~5500キロメートルの核弾頭および“通常弾頭”を搭載した地上発射型の弾道・巡航ミサイルのことである。INF条約はこうした兵器を米ソが全廃することを定めた条約であった。 なぜこのような条約が締結されたのか。ソ連は1970年代後半からSS-20と呼ばれるINFを欧州に前方配備し、「欧州諸国は狙えるが米国は狙えない」態勢を作り上げた。そのことによって欧州諸国に、「欧州に限定したソ連の核攻撃に対して、米国は自らが核攻撃されるリスクを冒してソ連に核反撃の威嚇を行うことはないのではないか」という拡大抑止面での不安を抱かせ、米欧間の離間(デカップリング)を図ろうとしたのである。 これに対して米国はじめ欧州の同盟国は、NATOの「二重決定」と呼ばれる方式で対抗した。すなわち、一方ではソ連に核軍縮交渉を呼びかけつつ、他方ではソ連がそれに応じるインセンティブを高めるために、NATO自身もINFを欧州に前方配備する方法を採用したのである。こうして、1980年代後半までに、欧州には東側のSS-20と西側のパーシングIIおよび地上発射型巡航ミサイル(GLCM)等のINFがひしめき合うようになった。 やがてソ連にゴルバチョフが登場すると、このような状況の危険性が改めて認識された。そこで米ソは紆余曲折の末にINFという特定兵器を全廃するINF条約を締結することに合意した。こうして米国側846基、ソ連側1846基のINFが全廃されることが決まった。この条約は、史上初の核軍縮条約であるとともに、史上初の特定兵器全廃条約でもあり、軍備管理・軍縮面で画期的なものであった。このINF条約の締結を境に、米ソは冷戦の終結に向けて協調姿勢を強めていくことになるのである。 上記の経緯から、INF条約は戦略核にかかわる条約だと考えられがちである。しかし、その規制対象に“通常弾頭搭載型のミサイルも含まれる”点を認識することは極めて重要である。ミサイルを外部から見ただけでは搭載弾頭が核なのか通常型なのかは判別し難い。査察や検証の有効性を確保するために、INF条約は核と通常型の双方の弾頭を搭載した「全ての射程500~5500キロメートルの地上発射型ミサイル(弾道および巡航を含む)」の保有を禁止した。この点が実は大きな今日的意味を持っているのである。 ■ ロシアの戦略的利益に適わなくなったINF条約 INF条約は冷戦末期の米ソ間の核軍縮における協調を象徴する条約であった。しかし、30年近く経過した今日、この条約を取り巻く環境はかつてとは一変している。戦略環境の変化が条約の存在意義を改めて問う状況を作り出しているのである。 冷戦終結後、INF条約を取り巻く状況に2つの変化が生じた。第1に、いくつかの国家で核開発が進められた。イランと北朝鮮が代表的だが、これらの国家は核兵器とともにその運搬手段たるミサイルの開発も進めており、イランはシャハーブ3、北朝鮮はノドンやムスダンなど、INFに相当する弾道ミサイル(準中距離弾道ミサイル=MRBMや、中距離弾道ミサイル=IRBMと呼ばれる)を保有するに至っている。これら、新たなINF相当のミサイル保有国に対する対応が問題となってきたのである。 第2に、INFに相当する通常弾頭搭載のミサイル配備を顕著に進める国家が登場してきた。こちらの代表は中国である。周知の通り、中国は1996年の台湾海峡ミサイル危機の経験に鑑み、有事の際の米国の西太平洋への戦力投射を防ぐ意図で、いわゆる接近阻止・領域拒否(A2/AD)と呼ばれる能力を増強させてきた。そして、その代表格が弾道ミサイルではDF-16やDF-21Cであり、さらに対艦弾道ミサイル(ASBM)とされるDF-21Dであり、加えて最近登場したDF-26C等であって、巡航ミサイルではCJ/DH-10等の各種ミサイルであったのである。 こうした戦略環境の変化は、米国よりもロシアの側に大きな影響を与えるものであった。米国の場合、INF相当の弾道・巡航ミサイルを開発または配備中の国家が近隣に存在しない。よって、少なくとも米国自身はこれらのミサイルを脅威に感じる必要がなかった。同盟国に対する拡大抑止の観点は必要であったが、敵対者のINF相当のミサイルの数が限られているうちは、ミサイル防衛(MD)での対処も可能であった。 だがロシアの場合、上記のようなミサイル開発国が全て近隣(INFの射程内)に位置している。そして、これら諸国のINF相当のミサイルの脅威に対して、有効なMD能力を持たず、INF条約に拘束されるロシア(厳密には、旧ソ連から条約義務を引き継いだベラルーシ、カザフスタン、ウクライナ等の旧ソ連諸国を含む)は、同種の兵器の配備によってそれらの脅威を相殺できないという問題が指摘されるようになった。 すなわち、戦略環境の変化の結果、INF条約はもはや今日のロシアの利益には適わないものと認識されるようになってきたのである。ロシアはこれまで折に触れてこの問題を提起してきた。 2005年、当時のS・イワノフ(Sergei Ivanov)国防相はINF条約からの潜在的な離脱の可能性について述べている。2007年、プーチン大統領(当時)も、米ロが第三国のINF相当のミサイル開発を念頭に条約のあり方を見直すべきだと提案している。ロシアはその頃からINF条約からの「ソフトな撤退(soft-exit)」を考え始めたと推測される。 ■ 米国務省報告書が問題視するロシアのINF条約違反 米国が7月29日に公表した軍備管理と不拡散に関する報告書によると、今回、米国がロシアのINF条約違反として問題視したのは、地上発射型の巡航ミサイルである。しかし、報告書中に同ミサイルの詳細についての記述はない。 この点、米ロ双方の報道や米国科学者連盟(FAS)のH・クリステンセン(Hans M. Christensen)氏によれば、違反とされたミサイルは、イスカンデル-K発射機から発射されるR-500ミサイルとされる。その射程は500キロメートル超とも2000キロメートルとも言われるが、既にエストニア国境付近のルガに配備されたとも見られており、事実とすればバルト三国をはじめとするNATO諸国にとって大きな脅威となりそうである。 ロシアのINF条約違反を巡っては、それ以外にもロシアが開発中のRS-26ルベズ大陸間弾道ミサイル(ICBM)が実はINFではないかとの疑惑が存在していた。このミサイルは2011年から実験が開始されたが、ICBMでありながらINFの射程で実験が行われ、これが条約違反に当たるのではとの指摘が行われてきた。ただし、米国はこれについてはINF条約に違反しないとして問題視しないようである。 また、上記イスカンデル発射機から発射される別の短距離弾道ミサイルである、SS-26イスカンデル-Mの射程が500キロメートルを超えているのではという疑惑も従来存在していたが、これも米国はINF条約違反であるとは見なしていないようであり、報告書中に記述はない。よって、米国が問題視するのはR-500と考えられる地上発射型の巡航ミサイルのみとなる。 ロシアがなぜこのようなミサイルをINF条約に違反してまで開発するかには諸説あるが、1つは既述のように、ロシア近隣のINF相当のミサイルを保有する国家に対抗する目的があるとみられる。特に、中国の弾道・巡航ミサイルに対抗するための開発という見方が有力となっている。 他方、ロシアには米国およびNATOが推進している欧州のMDを打破する目的があるとの見方も存在する。米国は2009年9月から段階的適合アプローチ(PAA)と称する欧州へのMD配備の取り組みを継続しているが、米国との交渉でこれを規制できなかったロシアが、新兵器によってMD拠点を攻撃するための手段を獲得しようとしているとの見方も存在している。 ■ 問われるオバマ政権の対応 弾道ミサイルであれ、巡航ミサイルであれ、ロシアのINF条約への違反は、オバマ政権が進める軍縮・軍備管理への取り組みに対する深刻な挑戦に相当する。よって、それに対してオバマ政権がいかなる対応を採るのかが注目されるところである。ところが、これまでこの問題に対するオバマ政権の対応は、かなり鈍いものであったと言わざるを得ない。 なぜならば、R-500ミサイルの最初の実験は2007年に行われたとされているからである。NYT紙によれば、オバマ政権は2011年末までにはその実験がINF条約違反の疑いがあることについて判断を固めていたという。それなのに、同盟国への通告は2014年1月まで遅れ、政権としての公式の断定と公表は現時点(7月末)まで遅れているのである。 このような遅延がなぜ生じたのか。背景として考えられるのは、オバマ政権がロシアとの核軍縮交渉の継続に未練を残したためではないかと推測できる。米ロ間では2011年に戦略核弾頭の保有数を1550発に抑える「新START条約」が発効しているが、オバマ政権はその後もその後継条約および米ロ間の戦術核の削減に関する条約について交渉を模索してきた。 そして2013年6月、オバマ大統領はベルリンで演説を行い、米ロの戦略核弾頭の数を新START条約の上限の3分の2、1000~1100発まで削減することが可能であるとする提案をロシア側に対して行った。すなわち、核廃絶に拘るオバマ大統領としては、ロシアのINF条約違反を公式に提起することによって、ロシアとのさらなる核軍縮交渉に向けた機運が萎んでしまうことを懸念したのではないかと推測できる。 しかし、このような姿勢は、現条約でさえ遵守しない相手と新条約の締結に向けて努力する、という本質的矛盾を孕んでおり、オバマ政権としても結局この問題を放置できない、との判断を固めたのであろう。よって、かなり時間が経過した後ではあったが、今回のINF条約違反断定の公表が行われたのであろうと考えられる。 そのため、オバマ政権としてももはやこれ以上はロシアの違反を見過ごすことができない段階に来ていると考えられる。それには、ウクライナ危機その他による米ロ関係の悪化により、さらなる核軍縮交渉の見通しが全く立たなくなったことも影響を与えている可能性が高い。すなわち、これはオバマ政権の「核なき世界」構想の重大な蹉跌と解釈することもできるのである。 ■ 「米国はどう対応すべきか」に関する2つの主張 オバマ政権の対応の遅れはともかく、現在、米国ではこの問題にどう対応すべきかを巡り、重要な戦略論争が展開されている。これは東アジアの戦略環境、ひいては日本の安全保障にも大きく影響する話であるので、日本人としても注目すべきだと考える。 ロシアのINF条約違反に対して、米国では大別して「条約遵守派」と「条約離脱派」の2つの対応が提起されている。 […]
2014/08/18 5:09
良いですね。日本の豊かな郷土料理の発掘、保護と継承。伝統的な地域毎の食材の保全、その調理法の継承。失われない様にして下さい。 — 《埋もれた郷土料理を探せ=全国に発信、和食を伝承-農水省》 2014.08.15 時事通信 地域に埋もれている伝統的な郷土料理を発掘し、食関連のブログなどを通じて全国に向けて発信する-。農林水産省がそんな取り組みを始める。世界無形文化遺産に登録された和食の保護活動の一環で、伝統野菜など地域の特産物の復活を図る狙いもある。2015年度予算概算要求に関連経費を計上する。 地方の風土や食材を生かした郷土料理は、昔からそれぞれの地域で愛され、受け継がれてきた。しかし洋食文化の浸透などとともに、作る家庭が減少。調理方法が伝承されなくなったり、食材となる地域固有の野菜や畜産物が生産されなくなったりした結果、食卓から姿を消しつつあるものも多い。 一方、NHK連続テレビ小説「あまちゃん」で取り上げられ、急に全国区の人気となった岩手県の「まめぶ汁」のようなケースもある。そこで農水省は、PR次第で全国の消費者に受け入れられる料理がまだ各地にたくさん埋もれているとみて、有識者検討会で探し出し、効果的な情報発信策を考えることにした。和食全体の保護と継承につなげたい考えだ。 http://www.jiji.com/jc/zc?k=201408%2F2014081500524&g=soc
2014/08/18 3:42
11日の「タイムズ・オブ・インディア」紙記事に続き、13日、韓国国史編纂委員会が「日本軍が強制連行した韓国人を虐殺して食べた」と主張、中韓メディアが報道。これも冤罪・誤判の疑いがあるBC級戦犯裁判等を根拠にしている模様。偶然でしょうか。現在、アンジェリーナ・ジョリーが捏造「日本兵人肉食小説」を基に製作中の映画「アンブロークン」と歩調を合わせた、「日本兵人肉食」プロパガンダが始まっています。 — 《韓国人が「日本軍の虐殺・人肉食に抵抗して蜂起」、米軍の写真資料で明らかに―韓国メディア》 韓国国史編纂委員会は13日、米国で保管されている米海軍の資料写真から、太平洋戦争末期に日本に強制徴用された韓国人が、日本軍による韓国人虐殺に抵抗して蜂起したことが分かったと明らかにした。韓国KBSワールドの中国語電子版が同日伝えた。 報道によると、写真は米国の国立公文書記録管理局が保管しているもので、1945年3月、南太平洋のある島で強制労働させられていた韓国人193人が、日本軍による虐殺行為に抵抗して蜂起したことが分かる。蜂起した人々のうち68人は日本軍の手の及ばない場所に逃げ、米海軍の助けで生き延びたという。 同委員会は「太平洋戦争末期に日本軍は極度の飢餓状態に陥り、韓国人を殺害して食べた。韓国人たちの蜂起はこうした野蛮な行為への抵抗だった」と指摘。日本軍が人肉を食べていたという状況は、米国立公文書記録管理局が保管する日本人の戦犯の裁判記録から明らかになっているとした。 (編集翻訳 恩田有紀) http://www.xinhua.jp/socioeconomy/photonews/392137/
2014/08/18 2:49
11日、インドの最大手英字日刊紙『タイムズ・オブ・インディア』が「大戦中、日本兵がインド兵捕虜を食べた」と題する記事を掲載。TOIは英字紙では世界最多発行数、朝日新聞と提携。冤罪・誤判の疑いがあるBC級戦犯裁判等を根拠にしている様であり、検証が必要です。 — 《「人肉食」も…旧日本軍のインド人捕虜への残虐行為、印紙報道 その背景とは》 2014.08.15 ニュースフィア 日本とインドは、長らく友好関係を築いている。しかし、第2次世界大戦当時、インドはイギリスの植民地であり、連合国側に属していた。このインドの軍隊と、枢軸国であった日本とが、戦火を交えたこともあった。このとき、日本軍が捕虜として捉えた、インド軍将兵に対して行った残虐行為を、インドの英字日刊紙『タイムズ・オブ・インディア』が詳しく伝えている。 【日本軍が捕虜としたインド軍将兵に対する非人道的行為】 1942年2月15日、日本は、当時イギリス領だったシンガポールを陥落させた。このとき、英領インド軍(英印軍)の将兵4万人が日本軍の捕虜となった。そのうち約3万人は、イギリス支配に抗しインドの独立を目指すインド国民軍に入隊した。この軍の設立にあたっては、日本軍が中心となって動いた。 しかし、入隊を拒んだ1万人は、日本軍の強制収容所での拷問を運命づけられた、と『タイムズ・オブ・インディア』は語る。収容所でのインド人捕虜の扱いは、非人道的なものだった。過重な労働、乏しい食料、絶え間ない暴行。そして捕虜が、生きたまま射撃訓練の標的とされることが、何度もあった、と記事は語る。 船で移送される際にも、寝る場所もないほど船室にすし詰めにされ、水や食料を満足に与えられず、目的地にたどり着く前に多くの者が死んだ、と記事は語っている。 【英印軍の将校らによる、日本軍の人肉食の証言】 「しかし、日本軍が行ったあらゆる残虐行為の中で、最も戦慄を覚えさせるものは、彼らが人肉食を行ったことである」と記事は伝える。 英印軍のある将校はこのように告発にする。「Suaidという村で、日本軍の軍医が、周期的にインド人捕虜収容所を訪れて、毎回、最も健康な者たちを選び出した。その者たちは、表向きは任務を果たすためということで連れ去られたが、彼らは決して戻ることはなかった」。さらに日本軍は、インド人捕虜ばかりでなく、ニューギニアの現地人さえも殺害し、食していたと主張する。 他の将校はこのように告発している。「自分と一緒にウェワク(の収容所)に行った300人のうち、50人だけがそこから出ることができた。19人は食べられた。日本人の医師――ツミサ中尉は、3、4人の小部隊を作り、インド人1人を何かの用事で収容所の外に遣わすのだった。日本人たちはすぐさま彼を殺害し、彼の体の肉を食べるのだった。肝臓、臀部の筋肉、大腿部、下肢、腕が切り取られ、調理されるのだった」。 【その他にも証言、証拠があるという】 記事では、これらの告発内容についての裏付けは伝えられていないが、この他にもさまざまな証言があるという。しかもそれらは、連合国が設置した戦争犯罪調査委員会に対する、宣誓証言として行われたと伝えている。その証言に基づき、何人かの日本人将校とその部下が裁判にかけられた。人肉食によって有罪が宣告され、絞首刑に処された将校の名前を、記事は挙げている。訴えられた日本人は、これらの告発を常に否認したそうだ。 1992年、田中利幸氏という日本人歴史家が、インド人や他の連合国側捕虜に対する、人肉食を含む、日本軍の残虐行為の明白な証拠を発見した、と記事は伝える(氏は現在、広島市立大学広島平和研究所教授)。その証拠がどのようなものかについて、記事は触れていない。氏は、1997年に『隠された惨事――第2次世界大戦における日本人の戦争犯罪』という本を英語で発表した。その本では、日本軍は食料の貯えが次第になくなったときに人肉食という手段に訴えた、という連合国側の下した判決が反論されているという。人肉食は上級将校の監督下で行われ、権力を表象化する手段として認識されていた、との主張だそうだ。 【英印軍の再評価の試みとも】 このように、日本軍が英印軍の捕虜に対して行った残虐行為の数々が、記事では列挙されている。しかし、記事の狙いは、日本軍の非道ぶりを暴くことだけではないようだ。 インドでは、インド国民軍は、イギリスからの独立に寄与した存在として、特別視されている。戦後、イギリスがインド国民軍将兵を裁判で裁こうとしたため、イギリスへの反感が爆発し、独立への機運が一気に高まった。その後、1947年8月15日にインドは独立を果たした。 反面、英印軍に対する評価は芳しくないようだ。記事によると、インドのナショナリストが第2次世界大戦を語るときには、ずっと、インド国民軍と邪悪な大英帝国の衝突として描かれてきたという。その構図では、英印軍はイギリスの手先の悪役だ。しかし、英印軍将兵が、日本軍の捕虜となり拷問を受けた際にも、忠誠を守り続けたことは、注目に値する勇敢さだと、記事は語る。 記事は、この勇敢さ、不屈の精神を、英印軍だけのものでなく、インド人一般のものとして捉えようとしている。英印軍将兵の示した忠誠心も、実はイギリスに対する忠誠心ではなく、同胞や上官、自分の所属する部隊に対してのものだった。そして、この忠誠心と、インド国民としての強いアイデンティティーとが結び付いて、彼らをあらゆる種類の困難に耐え抜かせていたのかもしれない、と語る。そしてこのアイデンティティーこそが、英国による支配を揺り動かしたのだろうと、英印軍の中にも、独立に寄与するところがあったとほのめかしている。 この記事を引用するかたちで、国際ビジネスニュースサイト『インターナショナル・ビジネス・タイムズ』(英国版)と、バングラデシュの『デイリー・スター』が取り上げている。前者は、人肉食を中心に、日本軍が行った戦争犯罪の非人道性に着目して、抜粋して伝えている。後者は、ほぼ人肉食のことだけを伝えている。 http://newsphere.jp/world-report/20140815-2/ (元記事) 《Japanese ate Indian PoWs, used them as live targets in WWII》 Aug 11, 2014, 06.00AM IST TNN[ Manimugdha S Sharma ]THE TIMES OF INDIA 写真 Japanese soldiers take aim at […]