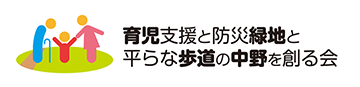カテゴリ:facebooklog
2014/07/26 7:31
歴史の捏造は是正しなければなりません。木本茨木市長の適切な処置を支持します。 — 《「朝鮮人強制連行」銘板撤去を要請 松井知事に茨木市長》 2014.07.25 産経新聞 大阪府が茨木市の旧軍施設跡に設置した銘板に非合法的な拉致をイメージさせる「朝鮮人強制連行」の記載が見つかった問題で、木本保平市長は25日、松井一郎府知事あてに銘板の撤去を要請する文書を送付した。 市関係者によると、要請文で木本市長は「歴史的根拠が不明確な記述が見受けられる」として、市が銘板を撤去することへの配意を松井知事に求めている。 銘板は平成6年、戦争の悲惨さを次世代に伝えるなどとして、翌年の戦後50年事業の一環で企画。7年12月、大阪警備府軍需部安威(あい)倉庫跡地の茨木市桑原の道路脇に、府が約80万円かけて設置した。 http://sankei.jp.msn.com/west/west_life/news/140725/wlf14072523590028-n1.htm
2014/07/26 7:17
《私たちに迫る中国の食品汚染|知らないでは済まされない5つのこと》 2014.04.01 小林謙太郎 今の時代ほど食の安全が問われているときは無いと思う。日本の最大の輸入先はアメリカで次に中国である。 輸入される食品は様々であるが、中国食品には残留農薬がたくさん含まれたものや食品添加物が多く含まれたもの、腐敗しているものなど様々なものがある。 中には中国製なのに日本で加工したから国産などとひどいものをあげたらきりがない。 中国産のものをすでにあなたは口にしているかもしれない。 食の現状を理解することがあなたの安全になりますように。 [目次] 1.中国食品の脅威 1−1.2倍の長さにのびるキュウリ 1−2.中国産ワカメ、水に漬けふやかしたら黒ビニールに 1−3.病死した豚の肉を羊肉と称して販売した 1−4.腐った月餅の餡だけ消毒して再利用 1−5.塗るだけで牛肉になる魔法のクリーム 2.日本に中国食品にくる理由 2−1.添加物の規制の緩さ 2−2.PM2.5は農村地帯にまで 2−3.地下水汚染が食品に与える影響 2−4.従業員の衛生管理の認識 2−5.農産物の汚染 3.なぜ日本に入ってきてしまうのか 3−1.検査にはお金がかかる 3−2.輸入食品の監視体制 3−3.自治体検査にも限界 3−4.中国食品の国内利用について 4.中国食品を買わないための防衛策 4−1.家庭で調理する機会を増やす 4−2.食の偽装問題 5.まとめ 1.中国食品の脅威 1−1.2倍の長さにのびるキュウリ スーパーでキュウリを買い、冷蔵庫に入れておいた。 1時間後に冷蔵庫を開けてみると、なんと2倍の長さに伸びていた。 1−2.中国産ワカメ、水に漬けふやかしたら黒ビニールに パッケージを開けて水に漬けふやかすと、なんとそれはワカメではなく、細かく刻まれた黒いビニールだったのである。 1−3.病死した豚の肉を羊肉と称して販売した 福建省州市の冷凍食品販売企業が摘発された。 冷凍庫には病死したブタの肉が山のように積まれており、 出荷中のトラックに積まれていたものも合わせて計32トンが押収された。 3人の容疑者が逮捕されたが、驚くべきことにそのうち2人は村政府に雇われていた職員。 病死したブタを回収し処理することが仕事だった。この肉を売れば金になると考え、横流しを始めたという。 独自に冷凍倉庫を建設、従業員3人を雇った食肉処理場を作るなど大規模な体制を整えていた。 昨夏から大規模な販売を始めており、すでに40トン弱を販売したという。 問題のブタ肉は広東省、江西省、湖南省などの食肉製品工場に流れ、大半は食卓に並んだとみられている。 1−4.腐った月餅の餡だけ消毒して再利用 月餅は中秋節(旧暦8月15日)に贈答品として利用されるが、この工場では、なんと1年前の餡を再利用していたという。腐ってカビだらけになった月餅から餡を抜き、薬品を加えて殺菌・消毒して再び月餅を創りあげていたのだとか。現場には悪臭が立ち込め、調理油の鍋には死んだネズミが浮いていたという。中国では、経済成長とともに贈答品としての月餅の需要が急増しており、ひと儲けしようと、悪徳業者が跋扈していると’12年9月26日付の中国紙「大粤網」が報じている。 1−5.塗るだけで牛肉になる魔法のクリーム このクリームを塗るだけで豚肉が真っ赤な牛赤身に大変身するという。 牛肉クリームはどんな肉も牛肉にしてしまう不思議なクリームというわけだ。 発表によると、牛肉クリームの原材料は「牛肉抽出物、食塩、砂糖、化学調味料、香辛料、デンプン等」だそうだ。ちなみに牛肉への変身所要時間は約90分らしい。 2.なぜこのような食品が増える? このような食品が増えるのは中国の衛生管理の文化によるものである。 2−1.添加物の規制の緩さ 中国で許可されている添加物の種類は1802種類。 […]
2014/07/25 13:15
例えば中国人は、「国防動員法」の規定により、日本に居住し働いていても中国政府の命令により中国の国防勤務を担う義務を負っています。我が国のどこに外国人がいるかを把握する事は、我が国政府の重要な責務です。国籍の調査をやめる事には反対です。 — 《風営法、本籍や国籍調査見直しへ 人権に配慮と警察庁》 2014.07.25 共同通信 パチンコや性風俗など風俗営業店の経営者に対し、従業員の本籍地や国籍を記載した名簿を作るよう命じる内閣府令について、警察庁が見直しの検討を始めていたことが25日、分かった。人権やプライバシーの保護を理由に、経営者に義務付けていた本籍や国籍の調査を求めないことにする。自民党などからも改正を求める声が上がっていた。 警察庁が所管する風営法は、営業所や事業所ごとに従業員名簿を備え付けるよう義務付けている。記載事項は、1985年の内閣府令(当時、総理府令)で、性別や生年月日、採用年月日などに加え、本籍地(日本国籍がない人は本人の国籍)も必要と規定。 http://www.47news.jp/CN/201407/CN2014072501000847.html
2014/07/25 10:38
様々な意味で良いと思います。—《防衛省:奄美市に陸自警備部隊》2014.07.25 毎日新聞 防衛省は24日、南西諸島の防衛力強化の一環として、奄美大島北部の鹿児島県奄美市に、陸上自衛隊の警備部隊を配備し、同島南部の瀬戸内町に訓練拠点を整備する方針を固めた。配備には400億円程度が必要と見込まれ、8月末の2015年度予算案概算要求に駐屯地の用地取得費などを盛り込む。8月上旬に武田良太副防衛相が奄美市を訪れ、政府の方針を伝える。 警備部隊は離島防衛の初動を担う。防衛省は、6月に同島の調査を行い、部隊運用や配備環境に適した場所の具体的な選定を進めてきた。 奄美大島では複数の自治体が誘致したが、奄美空港が近く物資搬入が容易で、市街地にも近い奄美市内に350人規模の警備部隊を配備。瀬戸内町に武器弾薬庫などを整備し、訓練拠点にすることとした。 政府は昨年12月に定めた防衛計画の大綱で、南西諸島の防衛強化を掲げた。宮古島と石垣島にも同規模の警備部隊を配備する方針で、15年度予算案に関連経費を計上する。http://mainichi.jp/select/news/20140725k0000m010154000c.html
2014/07/25 10:08
「専門家は『中国産食品への依存を見直さない限り第2、第3の事件は起きる』と警鐘を鳴らしている」。安全性を確保できない食品の輸入を従来より厳しく規制し、罰則を強化すべきです。各事業者の自主的な取組みでは解決できません。政府に対し声を上げましょう。現状では、真面目な事業者が損をするだけです。—《焼き鳥、ウナギ…高まる中国産依存度 大腸菌、殺虫剤まみれの食材ゴロゴロ》2014.07.24 ZAKZAK 中国の食汚染が再び、日本の外食産業に激震を走らせた。上海の食品会社が使用期限の切れた鶏肉を使っていたことが発覚し、取引のあった日本マクドナルドやファミリーマートが一部商品の販売を取りやめた。これまで本紙でもたびたび取り上げてきた中国産食品の危険性が、またもや明らかになった格好だ。専門家は「中国産食品への依存を見直さない限り第2、第3の事件は起きる」と警鐘を鳴らしている。 床にこぼれ落ちた肉塊を平然と調理鍋に投げ入れ、期限切れの肉を当たり前のように使い回す。 中国・上海のテレビ局が報じた工場内部の映像は衝撃的だった。 ずさんな衛生管理の実態が発覚したのは、上海の食肉加工会社「上海福喜食品」。同社では使用期限が半月過ぎた鶏肉や青カビが生えた牛肉を日常的に使っていたという。 同社から「チキンナゲット」の約2割を輸入し、国内全体の約4割に当たる約1340店で販売していた日本マクドナルドと、「ガーリックナゲット」用などに輸入し、約1万店で店頭に並べていたファミリーマートは、メニューの販売中止に追い込まれた。 今回の問題は、他の外食チェーンにとってもひとごとではない。 ガストなどを展開するファミリーレストラン最大手「すかいらーく」は「問題になった上海の会社との取引はない。中国食品の取り扱いはあるが、厳しい検査基準をクリアしたものだけを使っている」と強調。牛丼大手「吉野家」を展開する吉野家ホールディングスは「国内外含めて問題となった会社との取引はない」とし、「中国産食品の取り扱いについては担当者不在のため回答できない」とした。 日本ケンタッキー・フライド・チキン(KFC)は中国産鶏肉の使用はなく、「小麦の一部に中国産を使っているが、食品の安全管理には万全を期している」と話した。 主だった外食チェーンは安全性をアピールするが、消費者としては不安は尽きない。背景には、何度となく「食のチャイナリスク」に直面してきたことがある。 2012年には、抗生物質や成長ホルモンが過剰投与された『速成鶏』と呼ばれる鶏肉が、KFCの中国法人で使われていたことが判明した。日本では07年から08年にかけて毒ギョーザ事件が発生し、食べた10人が中毒症状を訴え、1人が一時重体に陥った。米国や欧州各国でも、中国産のペットフードによるペットの大量死が起きるなど事件が相次いでいる。 厚生労働省がまとめた「輸入届出における代表的な食品衛生法違反事例」で日本に輸入される際に摘発された中国産食品を調べてみると、危ない食材がゴロゴロと出てくる。 大腸菌まみれの「蒸し鶏」、漂白剤が残存する「乾燥きくらげ」、下痢性貝毒に汚染された「冷凍あさり(むき身)」、猛毒のヒ素が検出された「清涼飲料水」もあった。 違反事例は、食品専門商社などが輸入する際、厚労省のモニタリング検査などで汚染状況が判明したケースで、現実には日本国内に流通することはなかった。 だが、厚労省の医系技官で検疫官の経験がある木村盛世氏は「問題のある食品を(検疫所で)すべてシャットアウトするのは事実上、不可能。輸入食品の水際検査を行う食品衛生監視員はわずか399人(13年3月末時点)。検査機能を備えるのは横浜と神戸の検疫所だけで、マンパワーとインフラの両方が不足している」と説明。中国政府が、現地にしっかりとした検査機関を設置しない限り汚染食品の流入は防ぎようがないという。 『中国ニセ食品のカラクリ』(角川学芸出版)の著書があるジャーナリストの富坂聰氏は、中国の食汚染の要因について、「生産業者の規範意識の低さはもちろんだが、業者間の競争が激化していることも一因だ。一般論だが、彼らは悪いことをしているという認識の前に、コストを少しでも浮かせて利益を得たいという意識がある。競争を勝ち抜くため、期限切れのものを使ったり過剰に農薬を投与したりして不正を働く側面がある」と解説する。 食材の危険性がクローズアップされても日本の中国依存は弱まらない。 財務省がまとめた貿易統計によると、昨年度の中国産食品の輸入高は約8701億円。日本は最大の輸入相手国である米国の1兆2646億円に次ぐ高さで、00年度の約6503億円から約33・8%も取引量が増えた。 日本の食料自給率も1992年にカロリーベースで46%だったが、2012年には39%に減り、輸入食品頼みが続いている。 木村氏は「根本的な解決を目指すなら、日本の食糧事情を見直すべきだ。(この状況なら)中国産食品での第2、第3の事件はいつ起きてもおかしくはない」と語る。 中国発の「毒食品」にむしばまれる前に早めの対策が求められている。http://www.zakzak.co.jp/society/foreign/news/20140724/frn1407241820008-n1.htm