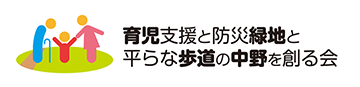7月7日。七夕の今日は、日中戦争(支那事変)の発端となった「盧溝橋事件」が起きた日です。先に発砲したのはどちらか、長年、議論となってきましたが、二十数年前、第三営の金振中営長が手記を公表、「日本軍が近づいたら銃撃してもよい」と命じていた事が分かり、「中国側の第一発」でほぼ決着しました。
—
《【子供たちに伝えたい日本人の近現代史】
(46)盧溝橋の一発で日中衝突》
■ 双方の「強硬論」が事件を拡大させた
中国・北京の中心部から南西十数キロ、永定河という川にかかる盧溝橋は、マルコ・ポーロが「東方見聞録」で絶賛したことから、マルコ・ポーロ橋とも言われる。
昭和12(1937)年7月7日、この橋の近くで日本軍と中国軍との間で衝突が起きた。橋が舞台になったわけではないが、付近一帯が「盧溝橋」と呼ばれていたこともあり、日本では「盧溝橋事件」と言われてきた。
この日の深夜午後11時ごろ、少し上流東側の荒れ地で夜間演習中の日本の支那駐屯歩兵第一連隊第三大隊に属する第八中隊が、背後の堤防上から銃撃を受けた。
発砲したのは、中国・冀察政務委員会麾下の第二十九軍第三営(大隊)とされる。冀察とは「河北省(冀)と当時のチャハル省(察)」という意味である。
日本軍が北京郊外に駐屯していたのは明治34(1901)年、義和団事件後の条約で認められており、英国など各国の軍同様、現地で演習も行ってきた。
発生当時、第八中隊では初年兵が行方不明(まもなく発見)になっており混乱したが、報告を受けた第三大隊は8日午前5時過ぎから中国軍への攻撃を開始、夕方まで戦闘が行われた。
事件をめぐって、どちらが先に発砲したかについて長年、日中双方で議論が行われてきた。しかし二十数年前、第三営の指揮をとっていた金振中営長が手記を公表、この中で「日本軍が近づいたら銃撃してもよい」と命じていたことが分かり「中国側の第一発」でほぼ決着した。
だが日本では、「西安事件」以来、国民党と日本を戦わせようとしていた共産党の党員が国民党軍の第三営にもぐりこみ、発砲したとの説も根強い。
いずれにせよ「衝突」は小規模だった。日本の陸軍中央は石原莞爾参謀本部作戦部長らにより「不拡大」方針がとられた。
その上で支那駐屯軍と冀察政務委員会との間で協議が行われ、11日には停戦協定が結ばれ、双方の軍はそれぞれの駐屯地に引き揚げた。これで一段落と思われたが、日中双方の政府の強硬姿勢が事態を深刻化させていく。
日本政府は不拡大方針にもかかわらず、新たに3個師団の現地への派遣を決める。その背景には二・二六事件鎮圧で陸軍の主導権を握った統制派内部の対中国政策をめぐる対立があった。
当時、関東軍参謀長だった東条英機や参謀本部作戦課長の武藤章らは、反日を強める国民党や中国共産党に対し「軍事的一撃を加えれば片付く」という「一撃論」をとった。その根底には強い中国蔑視があった。
これに対し石原らは「中国は決して侮れない。戦うのを避け本来の敵であるソ連に備えるべきだ」と唱えていた。両者は盧溝橋事件の処理をめぐっても対立、結局武藤らが押し切る形で軍事圧力を強めることになったのである。
一方、その中国国民政府の蒋介石総統には、北京(当時は北平)を中心とする河北省など華北地方を掌握しきれない苦衷と焦りがあった。
華北をめぐっては、満州国との間に「緩衝地帯」を置きたい日本の関東軍が昭和11年11月、北京城外の通州を「首府」とする親日的な冀東(河北省東部)防共自治委員会を発足させた。
これに対し国民政府も軍人の宋哲元を委員長として、北京に冀察政務委員会を設けて関東軍との緩衝政府とし、その南下を防ごうとした。このため日中間には一応の「平和」があった。
しかし西安事件以来、反日姿勢を強めた蒋介石は、盧溝橋事件の処理をめぐり宋哲元が日本に取り込まれると疑念を抱く。事件後、江西省廬山での会議で有名な「最後の関頭(せとぎわ)演説」を行い、日本への攻撃を宣言する。
「今や敵は北京の入り口まで迫ってきた。このままでは北京は第二の瀋陽(満州事変で関東軍の手に落ちた奉天)になる」
これを受けて、冀察政務委員会も二十九軍も反日攻勢へとカジを切っていく。(皿木喜久)
http://sankei.jp.msn.com/life/news/140223/art14022309300000-n1.htm