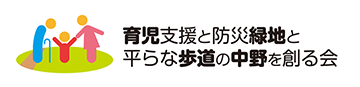ロシアがウクライナ東部で実行している「新しい戦争」の概念。「住民の蜂起と正規軍の軍事的圧力を組み合わせた、平時とも有事ともつかない状態を作り出し、公式の戦争を起こすことなく政治的目的を達成するという考え方」。中国の「キャベツ戦略」も類似しています。 — 《「ウクライナ危機3.0」の可能性を考える》 2014.11.04 Yahoo! JAPAN ニュース 小泉悠 以前の小欄で、収束と緊迫化を繰り返すウクライナ危機の性質について書いた。一度は停戦合意が成立するものの、その履行を担保するメカニズムが存在しない以上、危機は再燃し、しかもその度に既成事実が積み重ねられていくということが今回のウクライナ危機では繰り返されている。 そしてここしばらくの間に、ウクライナでは新たな緊迫化の兆候が顕著になってきた。 ■ これまでの経緯 イスラム国やエボラ出血熱騒動ですっかり忘れられつつある感もあるので、まずはここで簡単にこれまでの経緯を振り返っておきたい。 8月初頭、ウクライナ東部の親露派武装勢力はウクライナ政府軍の攻勢に対してほぼ壊滅寸前の状態に陥っていたが、8月半ば頃からロシアはロシア軍の直接介入を含む大規模な軍事援助を行い、瞬く間に形勢を逆転させた。 8月28日の拙稿をご覧頂ければ分かるとおり、一時期は壊滅状態に陥っていた親露派はわずか3週間ほどでウクライナ政府軍を押し戻し、版図を大幅に回復した。 さらにその後、親露派武装勢力はこれまで進出してこなかったウクライナ南部のアゾフ海沿岸地域まで一気に侵攻し、ドネツク州の暫定州都が置かれているマリウポリ(本来の州都であるドネツクは親露派に占拠されているため、こちらに疎開していた)の目前まで電撃的に侵攻した。以下の図は、ウクライナ国防安全保障会議(SNBO)が公表した、ウクライナ東部における最新の戦況図である。 ここに至り、ウクライナのポロシェンコ政権はついに、これまで拒否してきた親露派との停戦交渉を受け入れ、9月5日にベラルーシの首都ミンスクで停戦合意が成立したのである。 ■ なし崩しになる停戦 この結果、ドンバス(ドネツク・ルガンスク両州を併せた呼び方)では全体的に戦闘が下火になり、一時的に平穏が戻った。ただ、ドネツク空港周辺では依然として戦闘が続き、政府軍と親露派武装勢力の間で争奪戦が続いてきた。 両者がドネツク空港にこだわる理由ははっきりしないが、米USAトゥデイがウクライナの在米大使らに行ったインタビューでは、親露派はいずれ航空戦力を保有することを見越して空港を死守しようとしているという見方が示されている(もっとも、USAトゥデイが実際に現地の空港を防衛している親露派武装勢力司令官にインタビューを行ったところ「ロシアの飛行機ならどこでも望むところに降りるさ」と一笑に付されている)。 さらに停戦後もウクライナ政府軍と親露派武装勢力の戦闘は散発的に続いており、特に政府軍側はトーチュカ-U弾道ミサイルや多連装ロケットといった正規軍ならではの火力を活かした攻撃を継続した。 特に9月にはウクライナ軍の発射した弾道ミサイルが新学年の始まったばかりの学校に落下して生徒らが死亡するという痛ましい事件が発生したほか、10月にも親露派の占拠する地域の化学工場が弾道ミサイル攻撃で大爆発を起こしたことが広く報じられた。 また、ウクライナ軍はドンバス地域でクラスター爆弾を多用しており、民間人の犠牲者が増加していることに人権NGOヒューマンライツウォッチや国連当局者が懸念を表明するなど、ウクライナ軍の停戦違反に対して国際社会がフラストレーションを高めつつあることも見て取れる(ウクライナはクラスター爆弾使用を否定)。 もちろん、この間には親露派武装勢力や国境沿いのロシア軍による砲撃も続いていると見られるが、7月のマレーシア機撃墜事件当時、親露派武装勢力やロシアの国際的立場が大幅に悪化していた頃からするとやや潮目が変わりつつあるように見える。 また、9月には、ウクライナ国家親衛隊が占拠していた地域で大量の遺体が埋葬されているのが発見された問題で、ロシアは「ウクライナが虐殺を行っている」と非難を強めている。事件の真相は依然として明らかでは無いが、ウクライナ政府が軍の弱体化を補うために組織した数十もの自警部隊の中にはアイダル大隊のようにネオナチまがいの組織も多く、こうした部隊が虐殺を働いている可能性は否定できない。 凄惨な内戦の中で、ウクライナ側も「無垢の被害者」でばかりはいられなくなりつつあると言えよう。 ■ 2つの選挙 こうした中で、10月26日、ウクライナでは国会にあたる最高会議の総選挙が実施され、ポロシェンコ大統領率いる与党「ポロシェンコ・ブロック」が圧勝した。さらにこの選挙の結果、ロシアよりの立場を示すことが多かった共産党は全ての議席を失い(正確にはその前の7月の時点で議席を全て没収されており、その復活が叶わなかった)、議会での親欧米派の勢いは格段に高まった。 だが、総選挙はロシアの占拠下にあるクリミア半島では実施されず、ドンバスの2州でも親露派の支配地域では選挙が実施されなかった。 さらに11月2日、親露派支配地域でも「選挙」が実施された。 これにより、ドネツクではドネツク人民共和国(DNR)の「首相」を自称するザハルチェンコ氏が75%、ルガンスクでは同じくルガンスク人民共和国(LNR)のプロトニツキー「首相」が65%の得票で首長として続投することとなった。もっとも、この選挙は国際的な監視の下に実施されたものではなく、いずれも「自称」である。 ウクライナ政府はこの選挙を「まやかし」と呼び、承認しない姿勢だが、ロシアは同選挙の支持を表明。これに反発したウクライナ政府は、9月5日の停戦合意後に制定した「東部2州の特別の地位」を認めた法律の撤回を決定し、停戦合意自体が崩壊する可能性が高まってきた。 ■ 「親露派」はどこまで「親露」か ところで、これまで一律に「親露派」と呼んできた勢力の中身がここのところ大きく変質しつつあることにも触れておきたい。 8月頃までDNRの指導部の地位にあったイーゴリ・ストレリコフやアレクサンドル・ボロダイといった面々は、ロシアからやってきた大ロシア主義者であり、イデオロギー的な理由からかつてのロシア帝国の版図を取り戻そうという情熱に駆られた人々であった。 彼らの多くは歴史や哲学など人文系の高等教育を受けた人々であり、ストレリコフなどは中世の甲冑や第二次世界大戦中の軍服など、かつてのロシアの栄光を思い起こさせるコスプレ姿で度々写真に収まっているのは、彼らのこうした思想的傾向を端的に示すものと言える。 だが、親露派の劣勢と共にこうした人々は自らウクライナを去ったり、あるいは権力闘争に敗れるなどして次第に姿を消していく。代わって台頭してきたのが、ザハルチェンコのような地元出身の指導者や、ロシアが送り込んだ軍事のプロたちであった。 後者について言うと、ロシアは7月末から8月初頭にかけて、モルドヴァの分離・独立地域である「沿ドニエストル共和国」(もちろんモルドヴァ政府は認めておらず、いわゆる未承認国家である)からアンチュフェーエフ元「保安相」やカルマン元「副大統領」などを送り込み、DNRの要職につけはじめた。要するに、イデオロギーに駆られた親露派ではなく、よりクレムリンに忠実な分子で親露派の幹部を固め始めたのである。沿ドニエストルはロシアの後ろ盾によって成立しており、その指導部に対するロシアの発言力は強い。 だが、9月に入ってから、アンチュフェーエフは地元出身指導部との権力闘争に敗れて罷免されており、地元出身勢力とクレムリンとの間で確執があることが見て取れる。 今回の「選挙」を経てこうした体制がどう変化するかが、今後のひとつの注目点となろう。 ■ 紛争は再発するか? もうひとつの注目点は、もちろん、これが再び大規模な戦闘の再開につながるかどうである。 ウクライナ総選挙により、情勢が安定化に向かうのではないかとの期待感も一時期、国際社会では高まったが、親露派の独自選挙とこれに対するウクライナ政府の反発を見るに、その望みはどうも薄そうである。 そもそも、停戦合意後の一連の緊張緩和は選挙前のポロシェンコ大統領のポーズではないかとの見方は以前からあった。選挙を乗り切り、自身の基盤を固めたポロシェンコ政権が、再びドンバスの平定に向けて大規模な軍事作戦を再開するのではないかとの観測は根強い。 これに加えて、親露派の動向も不透明だ。ロシアの介入を得て版図を拡大した親露派であるが、4月の官庁占拠運動の中心地となったスラビャンスクなど、親露派にとっての「栄光の地」は依然として政府軍に奪回されたままである。「選挙による正統性」という旗印を得た親露派が、クレムリンの送り込んだ沿ドニエストル人脈の排除をさらに進め、再びスラビャンスクなどの奪回に出る可能性は否定できない。 さらに、仮に戦闘が再開することなく済んだとしても、ドンバスを親露派が占拠し続けている状況には変化はない。ポロシェンコ政権が「東部の特別の地位」を撤回した以上、徐々にドンバスを再びウクライナ政府の下へと再統合するというシナリオは崩れたわけで、このまま国家の分断が固定化する可能性が高いと考えられよう。 モルドヴァにおける沿ドニエストルの例や、グルジアの南オセチア及びアブハジア、アルメニアとアゼルバイジャンの間におけるナゴルノ=カラバフなどの例を見ても、一度分離独立地域が形成され、未承認国家化してしまった場合、法的親国への再統合は極めて困難である。 ■ ロシアの戦略 最後に、この事態の背後に居るロシアの戦略について触れておきたい。 9月5日の停戦後、ロシアはウクライナ東部及び国境地帯から部隊を撤退させたとも報じられた。しかし、ウクライナの軍事専門家ティムチュークは、依然としてロシア軍やロシアの支援を受けた武装勢力はウクライナ領内に留まり続けており、およそ3万人が4つの作戦集団を形成しているという(「キエフ・ポスト」2014年11月3日付け)。 ティムチュークは激烈な反露的記事を執筆し続けてきた人物であり、この数字がどこまで信用に足るものかは不明であるが、依然としてロシアがウクライナへの軍事援助を続けているらしいことは各種報道から推察できる。 また、ウクライナに隣接する南部軍管区はもともとイスラム武装勢力やグルジアを睨んで全ロシアの軍管区中で最も濃密な兵力配備が敷かれている地域であり、一度は撤退したロシア軍部隊を再展開させることはそう難しくない(これまでにもロシア軍はかなり短期間でウクライナ国境に部隊を展開させ、また撤退させるということを繰り返している)。 これについて注目されるのが、昨年以降、ロシアの戦略家達が口にし始めた「新しい戦争」の概念である。 住民の蜂起と正規軍の軍事的圧力を組み合わせた、平時とも有事ともつかない状態を作り出し、公式の戦争を起こすことなく政治的目的を達成するという考え方だ(もっとも、彼らのトーンはあくまでも、そのような「新しい戦争」を西側が旧ソ連やアラブで焚き付けている、というものであるが)。 もはや大規模な国家間戦争など起きない、というのがロシアの安全保障政策文書等における一種の決まり文句であったが、ロシア軍の制服組トップであるゲラシモフ参謀総長が2013年2月に発表した論文「予測における科学の価値」で、こうした「新しい戦争」こそが「21世紀の典型的な武力闘争の様態なのではないか?」と問うているのは示唆的だ。 もちろん、住民の蜂起を煽るような戦略は古来行われてきたものだし、非公然な正規軍の介入ならばスペイン内戦や朝鮮戦争など20世紀だけでも多くの事例がある。だが、興味深いのは、こうした手法を用いることで、大規模戦争が政治的に不可能になりつつある21世紀においても、欧州の目の前でこれだけの大規模騒擾を引き起こし、実際に一国の内政に干渉することができる、ということがウクライナで実証された点である。 こうした「新しい戦争」の状態、あるいはその恐れがある状態にウクライナ東部を置き続け、自国の勢力圏下からウクライナが脱そうとすれば紛争を再燃させて阻止する、というのがロシアの描いている戦略なのだと思われる。 本稿の冒頭で触れたウクライナ危機の周期的な再燃も決して偶然のものではなく、ロシアが戦略的に引き起こしていると見るべきであろう。 こうしたロシアの思惑がどこまで実を結ぶのかは現時点では明らかで無いし、単なる混沌を作り出してロシアの国際的立場を悪化させただけという見方も可能ではある。 ただ、ロシアがウクライナに仕掛けた「新しい戦争」への有効な対処が現時点では見当たらないこともまた事実であり、短期的にも見い出すことも難しそうだ。 ■ 小 泉悠 軍事アナリスト http://bylines.news.yahoo.co.jp/koizumiyu/20141104-00040499/ |